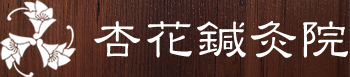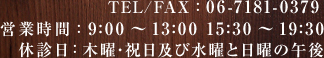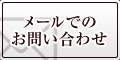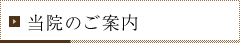中医学でみる「歯」
昨日は歯医者さんへ、半年に一度の検診に行きました 小さな虫歯はあるのですが、前回からとくに進んでいないので、また次回まで様子見となりました
小さな虫歯はあるのですが、前回からとくに進んでいないので、また次回まで様子見となりました 自分ではよく磨いているつもりでも、意外に歯ブラシの届いていない部分がけっこうありますね
自分ではよく磨いているつもりでも、意外に歯ブラシの届いていない部分がけっこうありますね
歯は中医学では「骨余」、骨の余りと考えられています。五臓では腎が関わります(腎は骨を主る)。
また上の歯茎には胃の経絡、下の歯茎には大腸の経絡が通じているので、歯と歯茎の状態から腎と胃腸の病変を推測することができます。
腎は前回取り上げた月経にも関わっていましたが、女性だけでなく男性でも同様に、大切な生理機能を担っています。次回、この腎について解説いたしましょう
中医学でみる「月経」
今回は、女性には避けて通れないもの、「月経」の話題です
前回同様、私事で恐縮ですが、今月は珍しく生理周期が乱れて平常より10日近く遅れました。長引く猛暑で体力が低下したためと思われますが、中医学では月経の不調をどのように捉えているのでしょうか?
月経は、中医学用語でも「月経」です。周期のほか、経血の色や量、質(サラサラであるか粘り気があるか)も重視します。正常な色は鮮紅色~暗紅色で、終始薄い色の出血しかない場合は血虚(貧血)が考えられます。量は基準が難しいですが、平均的には3~5日間持続し、初めと終わりが少なく中間の日が多くなります。質は薄い(ポタポタ、タラタラという感じ)のが正常で、血塊(ドロッとした塊)が出るのは血瘀によるものです。
周期は28日前後が正常ですが、これより7日以上短いのが「月経先期」で、血熱あるいは気虚により出血の制御ができなくなったものです。また7日以上長いのが「月経後期」で、血虚や寒邪により血が滞るために起こります。さらに周期が不規則になるのは「月経先後不定期(無定期とも)」といい、気血不調和と脾・腎の虚弱によるものが多いです。
一方、周期が正常でも経血量が通常より多いものを「月経過多」、少ないか期間が短いものを「月経過少」といいます。前者は「月経先期」と同じく血熱や気虚により、後者は血虚、血瘀、腎虚により起こります。
【参考文献】
神戸中医学研究会(編著):基礎中医学,燎原,1995
高金亮(監修),劉桂平・孟静岩(主編):中医基本用語辞典,東洋学術出版社,2006
いつもながら専門用語が多くて分かりづらいことと思いますが、このように分類することによって、お一人お一人の原因に合わせた治療が可能になるのです
マグネシウム
昨日は二十四節気の処暑でした。朝晩は風がいくらか涼しくなり、一昨日の夜には虫の音が聞こえました ……が、日中の猛暑はなかなか治まりませんね
……が、日中の猛暑はなかなか治まりませんね ゲリラ豪雨も頻繁で、今日も昼過ぎに突然の大雨と雷
ゲリラ豪雨も頻繁で、今日も昼過ぎに突然の大雨と雷 1時間足らずでやんだものの、今度は日が出て蒸し暑さが増しました
1時間足らずでやんだものの、今度は日が出て蒸し暑さが増しました
まだまだ熱中症に対する注意も必要です。私は今夏、スポーツドリンクの類をよく飲むようになりましたが、熱中症予防のほかに思わぬ効果がありました。
それは、「お通じが良くなった」ことです。もともと頑固な便秘ではないのですが、ときどき出にくくなることがありました。それがこの夏はわりと「快腸」なのです
おそらく飲料に含まれるミネラル、とくにマグネシウムが効いているのではないかと思います。5月26日付のブログでも少し触れた「塩類下剤」の主成分がマグネシウムです。浸透圧を利用して、腸管内に水分を引き込み、便を軟らかくして出しやすくする作用があります。
便秘にお悩みの方は、一度試してみてはいかがでしょう?(ただし冷蔵庫から出してすぐ飲むと冷たすぎるので、私は甘みの緩和も兼ねて湯冷ましを少々足します )
)
胃について
このごろ突然の雷雨が多く、残念ながら命を落とされた方もいます。皆さんの周囲は何事もないでしょうか?
朝晩は風が涼しくなってきたものの、日中は相変わらず残暑が厳しいですね。最近来院される患者さんの中には、長く続く暑さがこたえたものか、胃の不調を訴える方が多いです。
この「胃」は、中医学的にみると、どんな働きがあるのでしょうか。6月22日付のブログ「肝について」でも少し触れましたが、胃は六腑(胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦)の一つで、五行では土に属し、五臓の脾(7月22日付ブログ参照)と表裏関係にあります。(ちなみに五行と六腑では数が合わないので、小腸は「君火」、三焦は「相火」に属すとして、火が二つあります。)
①水穀の受納と腐熟を主(つかさど)る‥‥‥水穀とは飲食物のことです。飲食物を受け入れて、精微(栄養物質)にまで腐熟(腐らせ消化する意)するので、胃は「水穀の海」ともいわれます。飲食物は胃で腐熟されたのち、脾によって精微が吸収されて、肺に運ばれ全身を栄養します(注:肺の機能については後日解説いたします)。胃の受納と腐熟は、脾の運化と密接に関連しており、出生後に栄養を摂取し生命活動を維持するための基本的条件の一つであり、両者をあわせて「脾胃は後天の本」といいます。
②降濁を主り、降をもって和となす‥‥‥飲食物は胃で腐熟され、脾による清(栄養物質)の吸収・運輸を受けたのち、残余の濁(余分な水液や食物残渣)の部分は小腸から大腸へと下行します。飲食物の下方への運行は、胃気の降濁の機能にもとづいており、「胃は降濁を主る」といわれます。胃気の降濁が失調すると、胃気が上逆して受納や腐熟ができなくなるだけでなく、脾の昇清にも影響が及ぶので、「胃は降をもって和となす」ともいわれるのです。
③湿を喜(この)み燥を悪(にく)む‥‥‥胃は「水穀の海」で、受納と腐熟が順調に行われ、水穀の精微を産生して湿潤している状態がよいといえます。つまり、胃は津液で十分に潤されている状態が好ましく、乾燥すると本来の機能が果たせないということです。これとは逆に、表裏関係にある脾は「燥を喜み湿を悪む」といい、運化を主るという性質上、水湿が停滞してはなりません。このように、脾と胃の両者の機能は対立しつつ統一されて、飲食物の消化吸収と精微の運輸を行っています。
【参考文献】
神戸中医学研究会(編著):基礎中医学,燎原,1995
高金亮(監修),劉桂平・孟静岩(主編):中医基本用語辞典,東洋学術出版社,2006
「暑湿の邪」(7月3日付ブログ参照)によって脾が弱り、その不調が胃にも及びます。また冷飲食によって直接ダメージを受けることもあるでしょう。消化の悪いものを避け、何よりも疲労をためないよう、休養も極力とるようにしてください
お客様の声
今日はものすごい雷雨でした
 ちょうど昼休み中に天気が荒れだし、なかなか自宅から出られませんでしたが、ちょうど良い頃合いに雨が小降りになったので、急いで治療所に戻ってきました
ちょうど昼休み中に天気が荒れだし、なかなか自宅から出られませんでしたが、ちょうど良い頃合いに雨が小降りになったので、急いで治療所に戻ってきました
ところで昨日、本HPの「お客様の声」欄に新しく1件追加いたしました。患者さんに書いていただいた用紙をスキャンしてアップロードし、本文は別に手入力するのですが、打ち込みながら、気恥ずかしいような、恐れ多いような気持ちになります。ありがたい限りです。
もちろん自分としては、一人一人の患者さんに対して最良の、とはいかないまでも、よりよい施術を心掛けてはおります。しかし実際、治療を受けられている患者さんはどう感じられているのか、ご満足いただけているのかは分かりません。常に一抹の不安がつきまといます。
それでも時折このような温かいお声をいただくと、たいへん励みになります どんなに経験を積んでも「百発百中」というのは至難の業ですが、少しでもそのレベルに近付けるよう、これからも日々精進していく所存です
どんなに経験を積んでも「百発百中」というのは至難の業ですが、少しでもそのレベルに近付けるよう、これからも日々精進していく所存です
終戦記念日
今日は8月15日、終戦記念日です。毎年この日は、テレビの「全国戦没者追悼式」に合わせて正午の黙祷をします。
ふだん忘れがちな平和のありがたさを再確認し、二度と同じ過ちを犯してはならないと、自分に何ができるのか分からないながらも心に誓います。
3日間のお盆休みも今日で終わりですが、元気で働ける「当たり前」の幸せを感じつつ、明日からもがんばります
節電率不調
一昨日、今月の「電気使用量のお知らせ」がきましたが、なんと前年同月よりわずかに増えてました 毎日暑いの我慢してエアコンを控えてるのになぜ~
毎日暑いの我慢してエアコンを控えてるのになぜ~
……と思いましたが、よく考えたら昨年より患者さんが増えて、エアコンをつけている時間も増えたのと、7月後半から気温が上がり、35度以上の真夏日も昨年より多くなっているせいでしょう
自宅では30%近く節電できているので、個人的には相殺ということで。。。引き続き努力はします
マッコリ―米―
立秋が過ぎてから、日中は相変わらず暑いものの、朝晩の風は涼しくなってきました。季節は少しずつでも確実に進んでいますね
昨夜は久しぶりに飲みに行き、楽しく過ごしました 最近のお気に入りはマッコリです。とくにカシスマッコリやゆずマッコリなど、フルーツの入ったものがマイブーム
最近のお気に入りはマッコリです。とくにカシスマッコリやゆずマッコリなど、フルーツの入ったものがマイブーム
このマッコリ、主原料はお米です。日本人ならほぼ毎日口にするおなじみの食材ですが、中医学的にみるとどんな効能があるのでしょうか。
米は大きく分けて粳米(うるち米)と糯米(もち米)があります。今回は粳米について。
7月6日付ブログ「食養生の基礎知識」でご紹介した五味・五性では、粳米は甘・平です。
主な効能は、補中益気(胃腸を丈夫にして力をつける)、健脾和胃(消化吸収機能を回復させる)、除煩渇(イライラやのどの渇きを解消する)、止瀉痢(下痢を止める)、壮筋骨(体を強くする)。
中医学では「医食同源」として、あらゆる食材に上記のような性味・効能を見出しています。薬やサプリメントに頼る前に、日々の食事で体調管理できるのが理想ですね
【参考文献】
梁晨千鶴(著):東方栄養新書,メディカルユーコン,2005
夏翔・施杞(主編),丁鈺熊・銭永益・趙陽(副主編):中国食療大全,上海科学技術出版社,2006
節分・土用
明日は立秋。毎日のように続く猛暑も、明日からは残暑となります
昨日か一昨日、テレビのCMで「節分の恵方巻き」と言っていて、この季節に!?と思ったのですが、よく考えたら「節分」とは季節の変わり目。立春・立夏・立秋・立冬それぞれの前日を節分と呼ぶのですね。
節分と関連したものに「土用」があります。丑の日に鰻を食べる夏の土用がよく知られていますが、この土用もすべての季節にあります。夏の土用は立秋の前の18日間を指しますが、立夏の前の18日間が春の土用、立冬の前の18日間が秋の土用、立春の前の18日間が冬の土用です。また、それぞれの最初の日を「土用の入り」といい、最後の日が節分です。
実はこの土用の「土」は、中医学で用いる五行思想「木火土金水」の土に当たります。五行では春は木、夏は火、秋は金、冬は水に割り当てられていますが、それぞれの季節の中間に土が入っているのです。
古くから日本に伝わってきた五行思想が、現代の生活にも息衝いているのですね
頭の重量
先月見つけたツバメの巣を今日覗いてみたら、もぬけの殻でした 無事に巣立ったと思われます
無事に巣立ったと思われます
ところで、見上げる動作をすると後ろによろめくことがあり、そんな時に頭の重みを感じます。
一般に人間の頭部は、体重のおよそ10%の重さがあります。体重50㎏の人ならば約5㎏、結構な重さですね。
これを支えるために、首や肩の筋肉は日々緊張しています。居眠りの時に力が抜けると、首がガックリと前後左右に揺れることからも分かりますね。
日頃から猫背の人や、パソコン作業などで前のめりの姿勢になったり、携帯電話やスマートフォンを覗き込む時間が長かったりすると、首が前に傾いた状態が続き、首の筋肉に過剰な負担がかかって肩こりや頭痛などが生じやすくなります。
姿勢が悪くなると、脊柱全体のバランスが崩れ、腰痛や膝痛まで引き起こすこともあります。背筋を伸ばし、時々ストレッチをしましょう もちろん鍼で筋肉の緊張を緩和させるのも効果的です
もちろん鍼で筋肉の緊張を緩和させるのも効果的です
![]() 小さな虫歯はあるのですが、前回からとくに進んでいないので、また次回まで様子見となりました
小さな虫歯はあるのですが、前回からとくに進んでいないので、また次回まで様子見となりました![]() 自分ではよく磨いているつもりでも、意外に歯ブラシの届いていない部分がけっこうありますね
自分ではよく磨いているつもりでも、意外に歯ブラシの届いていない部分がけっこうありますね![]()
![]()